水平連携/垂直統合とは?水平連携と垂直統合の特徴や求められるシステム基盤構築を解説
企業の競争力維持・強化のためには、社会の環境変化に合わせて自社のビジネスモデルを構成・再編していくことが大切です。
ビジネスモデルの構成・再編するうえで重要な役割を担うのが、事業の統合・連携を推進する「水平連携/垂直統合」です。
本記事では、水平連携/垂直統合の概要やメリット、デメリット。そして、求められる情報システム基盤について解説します。ぜひご一読ください。

INDEX
水平連携/垂直統合とは

はじめに、水平連携と垂直統合の概要について解説します
水平連携とは
水平連携とは、企業が製品・サービスを消費者に提供する一連の工程のなかで、特定の工程を担う複数の企業が一体となって連携するビジネスモデルです。水平統合や水平分業とも呼ばれています。
例えば、同じ業界の製品の製造工程を担当する同業他社同士がM&Aにより統合し、市場シェアの拡大を目指すケースなどが考えられるでしょう。
垂直統合とは
垂直統合とは、企業が製品・サービスを消費者に提供する一連の工程において、自社の担当する工程を拡大していくビジネスモデルです。
一般的に、製品・サービスを消費者に提供するまでの工程は、調達や製造、生産などを担う川上工程と、流通・販売などを担う川下工程に分かれます。
例えば、これまで川上工程にあたる製造・生産のみ行っていた企業が、川下工程にあたる流通・販売もまとめて行うことで、自社で一貫したサプライチェーンの構築が可能です。
同一工程を担う複数の企業が横につながる「水平連携」に対し、1つの企業が川上から川下までを縦に包含する意味合いで「垂直統合」と表現されています。
水平連携のメリットとは

水平連携のメリットについて以下の3点を解説します。
スケールメリットの享受とは
水平連携によってスケールメリットを享受できます。
複数の企業が一体となることで、市場シェアを拡大し、スケールメリットによる競争力の強化が可能です。
これまで競合他社との過激な競争で消耗していた場合は、その状態から脱却して収益性の低下を抑止できるでしょう。
自社のコア事業に集中できるとは
自社のコア事業に注力できることも水平連携のメリットです。
自社の強みとなる事業・ビジネスに経営リソースを集中的に投下することで、高い業務効率性を発揮し、ビジネス競争力の強化を図れます。
管理コストの低減とは
水平連携による分業を行うことで、サプライチェーンのなかで自社が担当する工程が減るため、企業の管理コストを低減できます。
経営資源の限られている企業などにとっては、コスト負担が減って経営状態が安定しやすくなるでしょう。
また、生産工程や製造方法を変更したい場合は、他工程を担う他社との取引を変更・停止するだけで済むことも多く、市場環境の変化に対応しやすい点もメリットです。
参考記事
- サプライチェーンマネジメント(SCM)とは?SCMが注目される背景とその効果やメリットをご紹介 サプライチェーンマネジメントとは、サプライチェーンすなわち、製造する製品の部材調達から設計、製造、そして物流を経て、最終的にエンドユーザーまでの流れを統合的に見直し、全体の効率化と最適化を実現するための経営管理手法です。この管理手法を導入することで期待できる効果やメリットを分かりやすくご紹介します。
水平連携のデメリットとは
水平連携には前述したメリットがある一方、デメリットも存在します。主なデメリットとしては、以下の2点が挙げられます。
業務上の意思疎通が難しいとは
水平連携では、一連のサプライチェーンのなかで別々の企業同士が協業・連携するため、業務を進めるうえで意思疎通が難しい場合があります。
特に、企業同士の十分な合意がされないままM&Aが実行された場合、M&A後も組織や従業員間の摩擦が生じ、協力しづらい社内風土が形成されがちです。
意思疎通が難しいために経営上の意思決定スピードが遅くなり、市場環境の変化に柔軟な対応ができないリスクがあります。
独占禁止法や競争法に抵触するおそれがあるとは
水平連携を行う際は、独占禁止法や競争法などの法律に抵触しないよう注意を払わなければいけません。水平連携の規模や内容によっては、市場の独占・寡占に該当し、独占禁止法や競争法などの規制対象となる可能性があります。
水平連携を検討する場合は、社内外の法務の専門家とも密に連携して、法律面のケアもしっかりと行いましょう。
垂直統合のメリットとは

ここからは、垂直統合のメリットについて見ていきます。垂直統合のメリットは、主に以下の4つが考えられます。
自社サプライチェーンの強化による競争力向上とは
垂直統合によって一貫したサプライチェーンを保有することで、参入障壁が高くなり、競合他社や新規参入者に対して高い競争優位性を保てます。
サプライチェーンの全工程を自社の裁量でコントロールできるようになるため、スピーディかつ柔軟な事業の意思決定につながるでしょう。
製品・サービスの供給安定化や利益の安定化とは
垂直統合は、自社の製品・サービスの安定的な供給をもたらします。
取引先企業の都合や力関係に左右されることなく、一貫したルートでの供給ができるようになるため、利益の安定化にもつながるでしょう。
例えば、取引企業間の中間マージンのカットによって調達コストや販売コストを削減できた分、利益を確保できます。
ノウハウや機密情報を自社内に保持できるとは
製品の品質管理や製造方式などのノウハウを自社に蓄積することで、生産管理上の優位性を発揮できる点も垂直統合のメリットです。
サプライチェーン全工程におけるさまざまなノウハウを蓄積できるため、新たに事業領域や製品を展開する際にも活用できます。また、製造や生産にかかる機密情報を自社内に保持することで、情報保護や競争優位性の維持につながります。
サプライチェーンの全工程が自社内で完結すれば、各工程間で機密情報を含めた情報連携をスムーズに行えるでしょう。
価格決定権を持てるとは
垂直統合によって最終的な消費者への販売までを自社で行えるため、流通先の他社販売店に価格決定権を握られることがありません。自社で自由に製品・サービスの価格を決められます。
消費者との直接的なコミュニケーションにより、需要や潜在ニーズを発掘でき、今後のマーケティング施策にも活かせるでしょう。
例えば、消費者のニーズを直接的に捉えることで、新規市場の開拓やプライベートブランドの展開につなげることも可能です。
垂直統合のデメリットとは
水平連携と同様、垂直統合にもデメリットがあります。デメリットは主に以下の3点です。
自社のコアコンピタンスが希薄になるおそれがあるとは
垂直統合によってサプライチェーンの全工程を担う場合、これまで得意としていなかった領域・工程にも進出することになります。そのため、経営資源が分散し、自社のコアコンピタンスや専門性が希薄になるおそれがあります。
経営資源を広範囲に投下しなければならず、経営全体のバランスを保つために特定の領域の強化が難しくなることで、業務効率が低下しがちです。
設備投資や撤退費用などに多くのコストがかかるとは
これまでの本業に加えて、新しく進出した領域に関する設備投資や人的投資が必要となり、多くのコストがかかる点も垂直統合のデメリットです。
多くのコストがかかる一方、サプライチェーン全体を適切に管理できる保証はなく、うまく管理できない場合は負債化するおそれがあります。
また、市場環境の変化に応じて生産設備の変更や製造の中止を行う場合にも、サプライチェーン全体への影響が大きいことから、多くの変更費用や撤退費用がかかるでしょう。
垂直統合を行う際は、あらかじめ中長期的な視点で費用対効果を検討することが必要です。
取引先が自社グループ内に縛られる傾向があるとは
垂直統合をした場合、自社のサプライチェーン強化を促進するために、基本的には自社グループ内で取引を完結させます。自社グループ内で取引を完結させることは、情報連携をスムーズにするメリットがある一方で、社会の技術変化に後れを取るリスクも存在するのです。
例えば、他社に最先端の有益な技術がある場合、本来は他社と取引するのが望ましいものの、自社グループ内を優先するポリシーがあると取引が制限されます。
また、垂直統合の場合でも組織規模が大きくなると、水平連携と同様に体制変更や新技術導入時の意思決定スピードが遅くなるリスクもあるでしょう。
水平連携と垂直統合はどちらが優れているのか
水平連携と垂直統合のメリットやデメリットについて解説しましたが、両者はどちらもビジネスモデルの一種であり、どちらが優れているかは一概には言えません。
水平連携では柔軟な軌道修正を行える反面、自社の事業領域が広がりにくい懸念があります。一方の垂直統合では自社のサプライチェーン強化を図れるものの、投資失敗による負債化リスクがあります。
経営においては、自社のビジネス環境や業界動向、競合他社などの状況を見極め、適切なビジネスモデルを選択することが重要です。
例えば、水平連携の企業例としてApple社があります。
Apple社は、iPhoneやiPadのOSや一部ソフトの開発は自社で実施している一方、生産はEMS(電子機器受託生産サービス)を利用して外部の企業に委託しています。
垂直統合の企業例では、ユニクロ社(ファーストリテイリング傘下)が広く知られています。
同社は、SPA(製造型小売業)手法を採用し、自社のオリジナル製品の開発から販売までを一貫して行っています。店舗にて消費者と直接つながれる強みを活かし、消費者ニーズ起点で製品開発をスピーディに進めていくことで、トレンド変化が激しいアパレル業界において大きなシェアを維持しています。
水平連携/垂直統合を支える情報システム基盤とは
水平連携/垂直統合を支える情報システム基盤として代表的なのが、自社のサプライチェーンの適切な管理などを行える「ERPシステム」です。
ERPシステムは、企業全体最適の視点で社内の各種データを収集・分析し、経営上の意思決定を迅速に行うために利用されます。ERPシステムには生産管理機能や販売管理機能などがあり、一連のサプライチェーン工程の管理が可能です。
加えて、ERPをコアに据えつつ、さまざまな周辺ソリューションとの連携を図ることも大事なポイントです。
例えば、SAP社が提供するSAP S/4HANAをコアに、周辺ソリューション連携を通じて、ビジネスエコシステムを実現できます。
水平連携、垂直統合のどちらのビジネスモデルにも対応するためには、変化の激しい時代にも対応できるERP(リアルタイム性、分析の高速化)の活用が適しているでしょう。
まとめ
水平連携と垂直統合はいずれもビジネスモデルの一種ですが、それぞれ異なる特徴を持ちます。
変化の激しい時代のなかで生き残るためには、水平連携と垂直統合のどちらのビジネスモデルにも対応できるように構えておくことが重要です。
そのためには、一連のサプライチェーン工程の管理ができるERP(リアルタイム性、分析の高速化)の活用がポイントです。
例えば、SAP社が提供するERPであるSAP S/4HANAや、クラウド型のサプライチェーン管理ソリューションのSAP Integrated Business Planning(SAP IBP)を活用することで、社会の環境変化にも柔軟に対応できるビジネスエコシステムを実現できるでしょう。SAP IBPは、サプライチェーンの計画やプロセス管理を最適化し、そして基幹システム(SAP S/4HANA)などとの連携が可能です。
SAP IBPなどのシステムを効果的に活用しながら、ビジネスモデルへの対応力や競争力の強化を図っていきましょう。
参考記事
- SAPとは SAPは、「経営・業務の効率化」や「経営の意思決定の迅速化」を実現することを目的に、多くの企業で導入されているITソリューションです。このITソリューションにより、企業の経営資源である「人・モノ・金」の情報を一元で管理ができ、そして経営の可視化を実現できます。本コラムでは、SAPについて詳しく解説をしていきます。
- ERPとは?基幹システムとの違いや導入形態・メリットと導入の流れを解説 ERPパッケージとは、企業の基幹業務の統合化を図るERPを実現するソフトウェアです。ERPを導入することで、業務の効率化やコスト削減といったメリットを得られます。もちろんデメリットもあります。本コラムでは、ERPパッケージについてまとめ、導入を実現するためのポイントを分かりやすく解説します。
関連サービス
- コンサルティング/PoC SAPソリューションやそれを含むエコシステムをどう使っていくのか、そしてその使い方を提供するのがコンサルティングです。システムのライフサイクル全般に渡りサービスを提供し、PoCを行うことで、機能の妥当性や実現可能性の評価も行います。
関連資料
-
基幹システムソリューションガイド(大全)
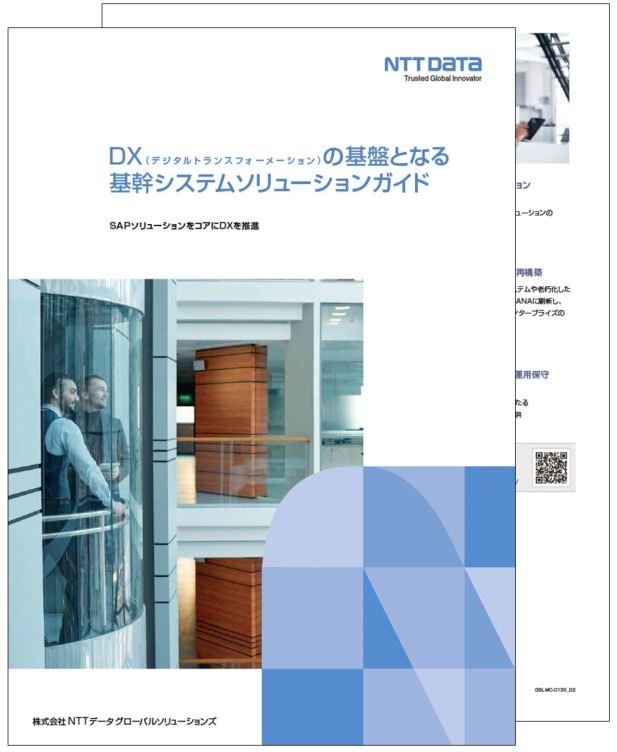
NTTデータ グローバルソリューションズが提供するお客様のDX(デジタルトランスフォーメーション)を実現するためのソリューションガイドです。ぜひ、ご一読ください。 ダウンロード
-
不確実な時代に応える変化に強いものづくりの実現

多くの製造業が抱える大きな課題として「不確実性の高まる世界」への対応が挙げられます。
こうした先を見通すことが難しい時代だからこそ、「変化に柔軟に対応できる強いものづくり」の実現が強く求められます。そこで、NTTデータGSLは今まで部分最適で行ってきた「設計と生産」に着目し、その両者の壁を解消に、いかにコストを抑え、そしてスピーディに生産と設計の連携を深める、不確実な時代を勝ち抜く「データに基づくものづくり」の実現を提案します。 ダウンロード